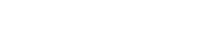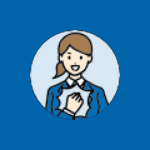詐欺
【2024年最新】総務省職員や刑事を騙り口座情報や金銭を要求される偽逮捕詐欺を徹底解説!
昨今、刑事を騙って個人情報や金銭を詐取する、スマートフォンの通話アプリを狙った「偽逮捕詐欺」の被害が若い世代にも増加しています。年々複雑化する詐欺の手口から被害から身を守る意味でも、偽逮捕詐欺の概要や最新の手口、被害に遭った場合の対処方法、詐欺の被害について相談できる機関など、わかりやすく解説していきます。
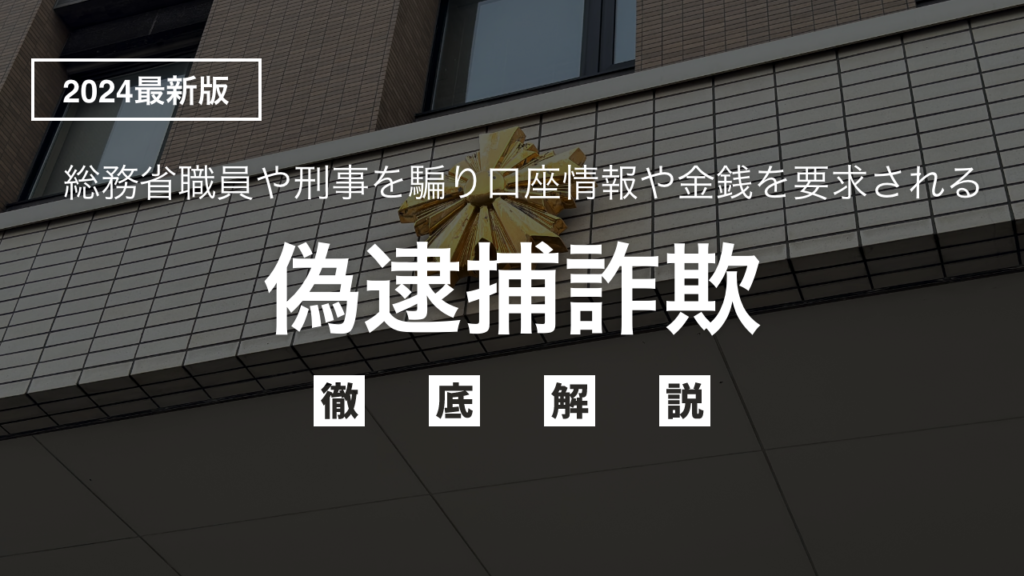
arrow_drop_down 目次
昨今、刑事を騙って個人情報や金銭を詐取する、スマートフォンの通話アプリを狙った「偽逮捕詐欺」の被害が増加しています。
こちらの詐欺は、ある日突然、総務省をはじめとする公的機関の職員を名乗る人物からスマートフォンの通話アプリに電話がかかってくるところから始まります。
電話口の相手は、「あなた名義の携帯電話が特殊詐欺に悪用されているため、身に覚えがなければ、〇時間以内に〇〇警察署に通報して被害届を出してください。」などと、自身の住所を正確に把握していることから、通話を続けてしまい、詐欺の被害に遭ってしまうといったものです。
以前は、「特殊詐欺」に巻き込まれる傾向の高い人物像として固定電話を使用する高齢者や資産家といったイメージがありました。
しかし、年々複雑化する詐欺の手口により、スマートフォンを普段から活用する、若い世代にも被害が広がっています。
今回は、「偽逮捕詐欺」の被害から身を守る意味でも、偽逮捕詐欺の概要や最新の手口、被害に遭った場合の対処方法、詐欺の被害について相談できる機関など、わかりやすく解説していきます。
この記事が「偽逮捕詐欺」についての対策を学びたい方や被害に遭ってお困りの方の一助となれば幸いです。
「偽逮捕詐欺」とは
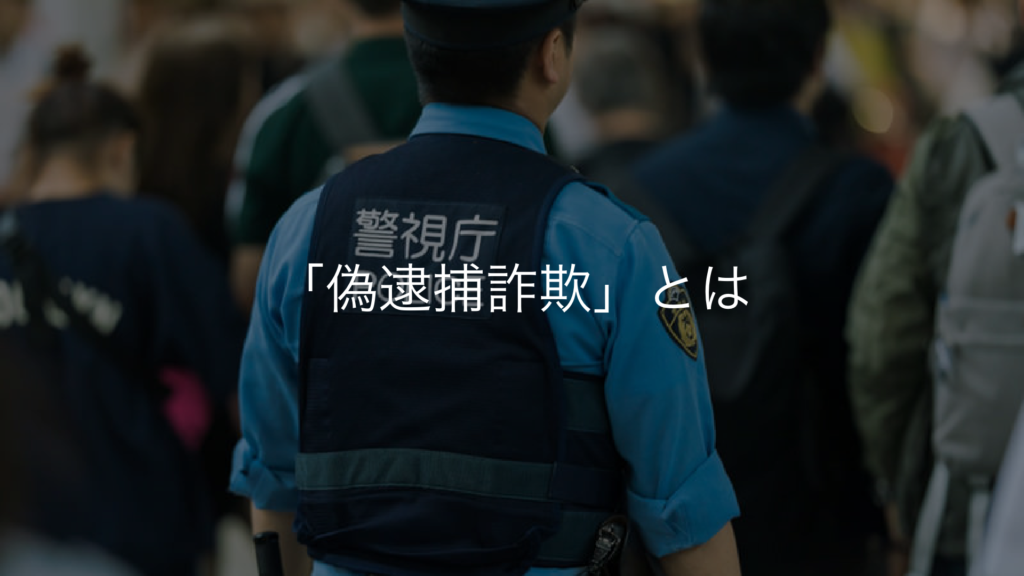
社会的信用度の高い公的機関の職員であると偽ることで、被害者を心理的に操作し、詐欺を働く悪質な手口のため、注意が必要です。
本記事のメインテーマである「偽逮捕詐欺」は、詐欺の手口が複雑であるため、詳細については、次の章において手口と流れとしてご説明させていただきます。
「偽逮捕詐欺」の手口と流れ

こちらの章では、「偽逮捕詐欺」の手口と流れについて、注意喚起の意味を込めて、最新の事例をもとに解説させていただきます。
次にご紹介する手口に少しでも当てはまる場合には、詐欺の可能性が高いため、直ちに振込をストップしましょう。
万が一、詐欺師が指定する口座に振り込んでしまった場合には、1人で抱え込まず、早急に弁護士などの専門機関に相談することを推奨します。
それでは、各項目についてご紹介します。
1. スマートフォンの通話アプリに公的機関の職員から電話がかかってくる
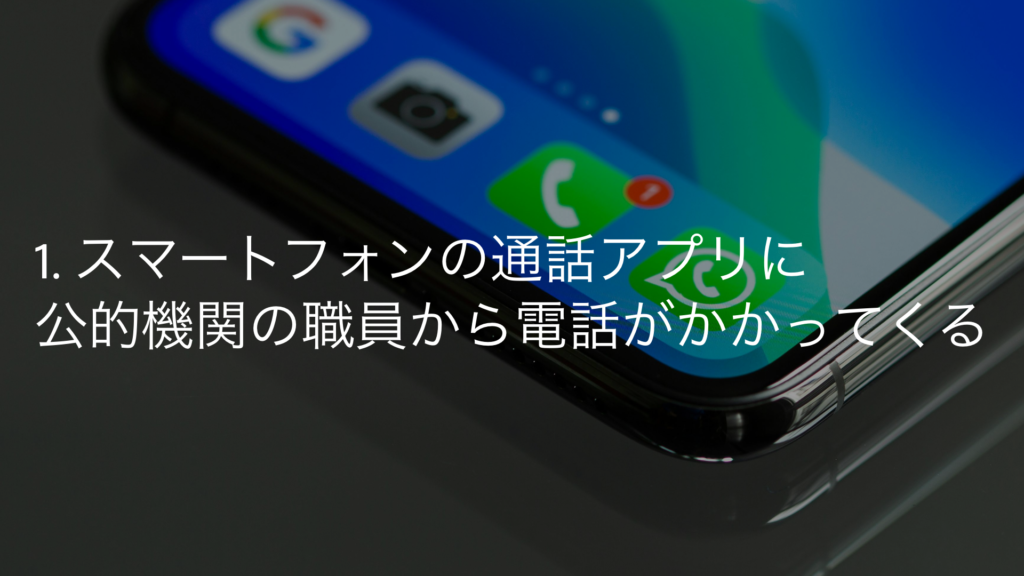
ある日突然、総務省をはじめとする公的機関の職員を騙る人物からスマートフォンの通話アプリに電話がかかってきます。
電話口の相手は、次のような話をします。
「あなた名義の携帯電話が特殊詐欺に悪用されています。身に覚えがなければ、〇時間以内に〇〇警察署(実在の警察署)に通報して被害届を出してください。」
2. 公的機関の職員から警察に電話を転送され、被害届の提出を求められる
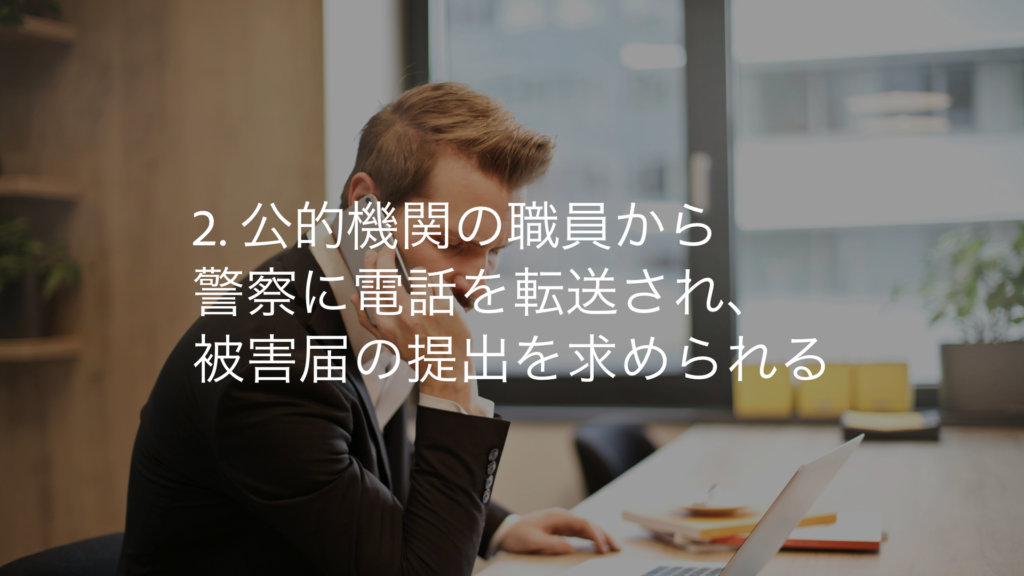
通話を続けると、公的機関の職員から警察に電話が転送され、電話口に刑事が登場します。
相手方は、「〇〇警察署(実在の警察署)の刑事・〇〇」という自己紹介とともに、時間指定の期限付きで被害届を出すよう求められます。
指定の時間までに被害届を提出できないことを伝えると、「在宅でも被害届の提出は可能である」と手続を進めることになります。
ここで注意したい!「被害届」とは
「被害届」とは、犯罪被害に遭ったことを警察に伝える書類です。
被害者が未成年であるケースや亡くなっており、被害を伝えられない場合には、法廷代理人でる親権者等による提出が可能です。
被害届には、次のような内容を記載します。
- 被害者の住居・氏名・年齢・職業
- 被害に遭った年月日時・場所
- 被害の詳細
- 被害金品
- 犯人の住居・氏名・人相・着衣・特徴など ※把握している場合
- その他参考となる資料(医師の診断書・遺留物など)
被害届について、「受理されるにはどのような書類が必要であるか」「受理されるための見通しはあるか」等、お困りのことがありましたら、弁護士に相談することも検討しましょう。
3. 在宅での調書
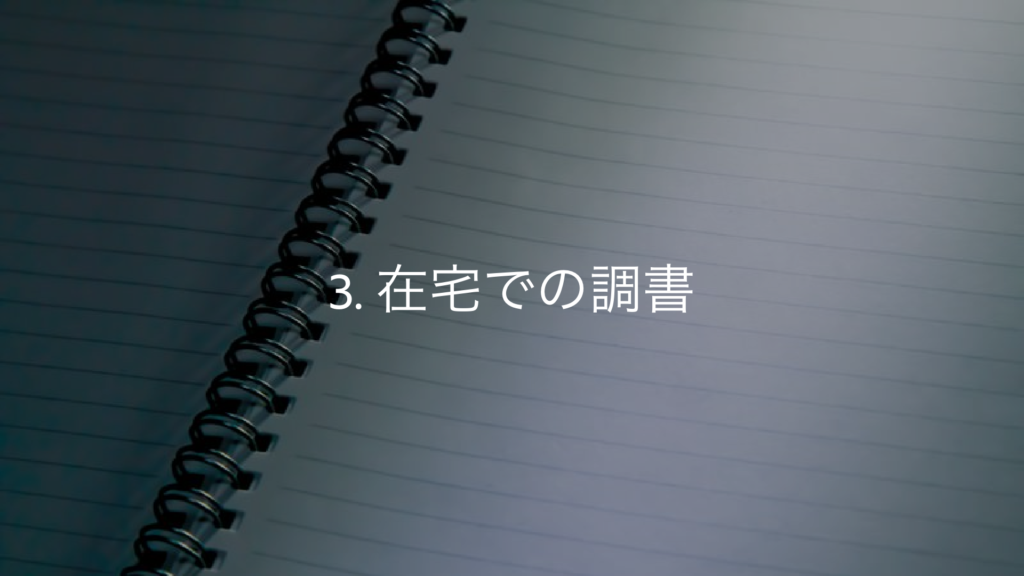
次の手順で始まるのは、〇〇警察署(実在の警察署)の刑事・〇〇を名乗る人物による、携帯電話の不正利用の被害届を提出するための「在宅調書」です。
移動後、調書時の日時・氏名・生年月日・住所などの情報を伝えることになります。
4. 別の容疑がかけられる
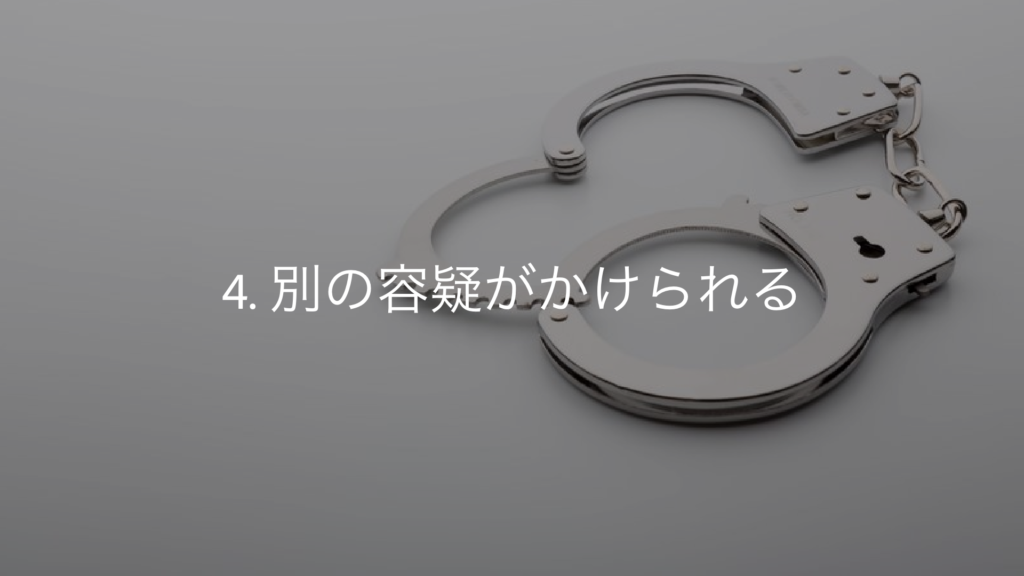
被害の詳細について述べる際に、「自身の携帯電話が特殊詐欺に悪用される身に覚えがない」と返答するのが一般的でしょう。
刑事を騙る人物からさらに、あなたに別の特殊詐欺についても容疑がかけられている、と伝えられます。
具体的には、次のように話が進みます。
- 「あなたは〇〇銀行〇〇支店(実在する銀行の場所)で起きた特殊詐欺の重要参考人になっています。」
- 「その理由は、逮捕時の押収品の中に、あなた名義のキャッシュカード(または預貯金通帳)があったためです。」
- 「主犯格はあなたのキャッシュカード(または預貯金通帳)を購入し、被害額の〇〇をキャッシュバックしたと供述しています。」
- 「SNS等でキャッシュカードを売買していませんか?」
「警察のデータベータであなたの名前を検索した」と信憑性があるかのような偽りの情報を持ち出す場合もあるため、注意しましょう。
口座売買は違法行為です!
有償・無償を問わず、口座情報を他人に提供する行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)」第28条において、禁止されています。
また、インターネットバンキングのログイン情報(ID・パスワード・認証コード)を第三者に提供する行為も、口座売買と同等の扱いです。
重ねて、口座を売る側(口座名義人)だけでなく、買う側も罪に問われることにご留意ください。
売る側→口座名義人、買う側→犯罪利用のため、他人の口座情報を購入する、という関係性があります。
取引された預貯金口座は、特殊詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪に利用される可能性が非常に高く、意図せずとも犯罪を助長させることになりかねません。
大きなトラブルから身を守るためにも、個人情報や銀行口座の取り扱いには、くれぐれも慎重になりましょう。
5. 捜査を進めることを名目にした「LINE」でのやり取り

〇〇警察署(実在の警察署)の刑事・〇〇を名乗る人物は、今後の捜査を進めるためと、LINEの交換を求められます。
この後、特殊詐欺事件に関する質問に対し、メッセージや通話機能でやり取りが続けられます。
6. LINEで重要データが送付される
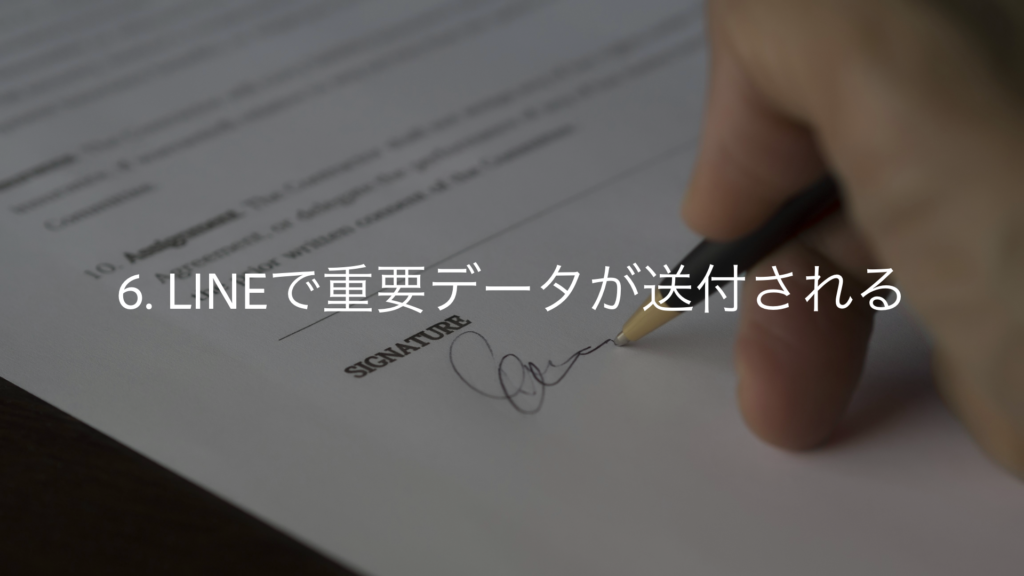
重要書類には、次のような内容が記載されています。
- 捜査が終了するまで口外しないこと
- 特殊詐欺グループの幹部の印
- 特殊詐欺の犯罪者リスト(名前・顔写真付き)
特に、特殊詐欺の犯罪者リストにご自身の名前や顔写真が掲載されており、身に覚えがないのにも関わらず容疑がかけられていることで、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。
しかし、常識的に考えて、特殊詐欺に加担したと疑われる重要参考に対し、証拠資料のデータを送るでしょうか。(本当に、特殊詐欺組織の一員として犯罪に加担しているのであれば、データを見た時点で仲間に逃げるように伝えるといったことも考えられます。)
これらは被害者を騙すための手法であり、実在の人物の名前や写真は無断使用されている可能性もあるため、1人で抱え込まず、早急に弁護士などの専門機関に相談することを推奨します。
7. 厳しい追及
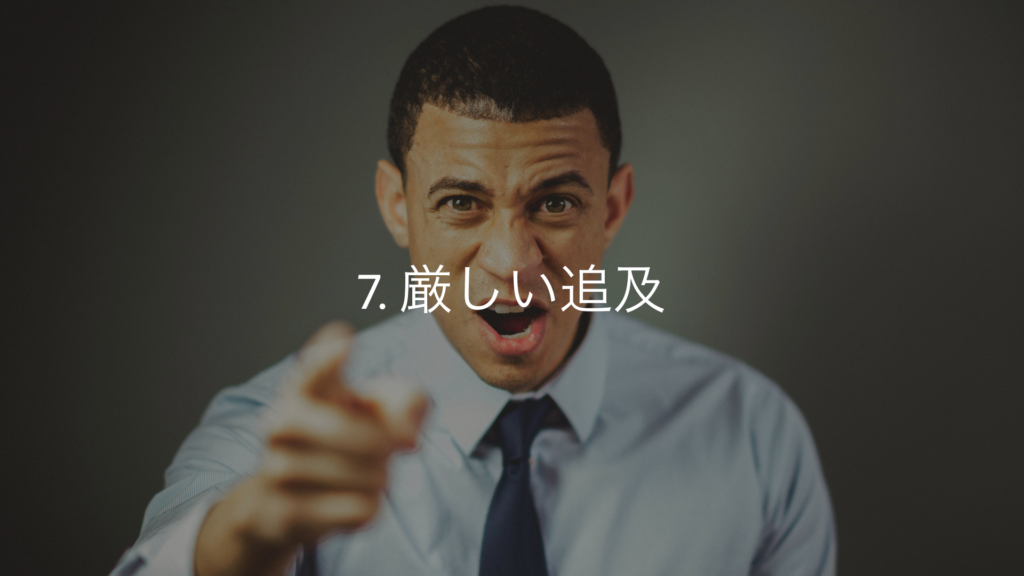
真実を伝えても信用してもらえず、犯人扱いされるといった事例も報告されています。
また、先にご紹介した「守秘保持契約書」等の重要データには、口外しないよう記載されているため、誰にも相談できず、被害者を精神的に追い詰めます。
8. 資産リストの提出を要求される
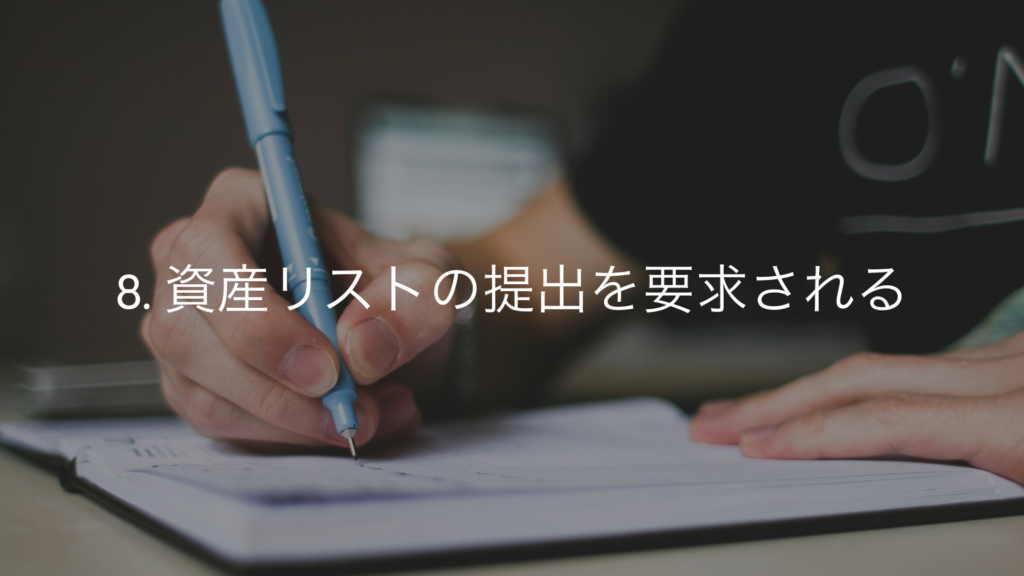
具体的な資産として記載するよう求められるのは、一般的に次の項目です。
- 預貯金(銀行口座の情報・預貯金残高・インターネットバンキングの情報等)
- 有価証券(株式・債券・手形・小切手等)
- 不動産
もちろん、資産リストを送付したとしても、正当な捜査が進められることはありません。
LINEは便利なツールである一方、残念ながら、第三者になりすまして悪事を働くこともできてしまうのです。
金融機関名・口座種別・口座名義・口座番号・支店番号・暗証番号・インターネットバンキングにログインするのに必要な情報( ID・パスワード・認証コード)
9. 資産リストの提出を拒否すると「逮捕する」と脅される
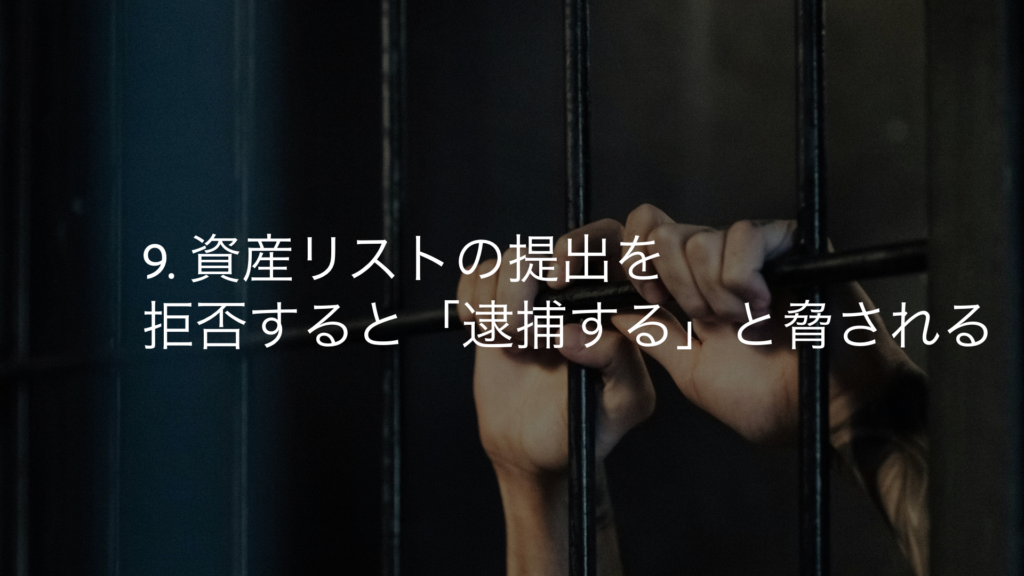
やり取りしている相手がたとえ刑事を名乗っていても、LINEというツールで預貯金口座の情報をはじめとする個人情報を送付するのは抵抗がある方が多いのではないでしょうか。
資産リストの提出を拒否した場合、刑事を名乗る詐欺師は、被害者に対し、次のような揺さぶりをかけます。
さらに、次のように話が続けられます。
- 「逮捕を免れたければ、資産リストを提出してください。」
- 「資産リストを提出することにより、操作に協力的な姿勢を見せることができ、逃亡の恐れがないとして、優先捜査を行えます。」
- 「優先捜査は、口座凍結されたり、勾留されずに捜査を進められるため、家族や会社にバレずに手続を完了できますよ。」
詐欺師の話を信じてしまい、預貯金口座の情報を伝えてしまった場合、口座から不正に送金されてしまったり、銀行口座自体を別の特殊詐欺に悪用されてしまう可能性が高いため、くれぐれも注意しましょう。
「偽逮捕詐欺」に遭った場合の対処法

こちらの章では、偽逮捕詐欺に遭ったらはじめにやるべきことについて、ご紹介します。
前提として、詐欺行為は罰せられるべき犯罪です。
実際に入金する前に信頼できる人間に相談したり、トラブルに巻き込まれた場合には、詐欺の相談窓口や最寄りの警察へ助けを求めることで、被害の拡大を防止することに繋がります。
1. 素早く証拠を確保する
詐欺行為を証明し、後の被害金返還手続や民事裁判を提訴する場合には、早急に証拠を集めることが重要です。
弁護士や警察等に解決へ向け動いてもらうためにも、次の情報を迅速に確保する必要があります。
- 「偽逮捕詐欺」に遭った流れ
- 現在の状況(詐欺師の名前や所属部署または管轄など)
- 詐欺師の情報(電話番号やメールアドレス)
- 契約書などの書類(守秘保持契約書など)
- 通話記録
- 詐欺師とメール等のツールでやり取りした記録
- 詐欺の取引日時
- 被害額
- 振込の明細書
- 詐欺師の口座への取引履歴(店番号・口座番号・氏名など))
記憶が鮮明なうちにメモを取ったり、日付やURLが紙面に残せることから通話記録や電話番号のスクリーンショットなどの証拠資料をプリントアウトすることを推奨します。
2. 追加の支払いや通帳・カードの受け渡しをしない
偽逮捕詐欺であると気付いた際に、被害額を取り返そうと、詐欺師の要求に従い、追加の入金に応じてしまう方も少なくありません。
実際に指定された口座に振込をした場合でも、特別なアクションをもらえることはなく、連絡が途絶えてしまうことがほとんどです。
まずは冷静になり、起きてしまった出来事を客観視するとともに、その場での判断や行動を控えることが最も重要です。
これ以上被害を大きくしないためにも、早い段階で法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応策についてアドバイスを仰ぎましょう。
3. 詐欺師と連絡しない・直接会わない
自分を騙したということで、詐欺師に対し「早急に返金してほしい」「弁護士に相談する」「今すぐ警察に通報する」と、感情的になったり挑発したりすることは避け、冷静に行動するのが被害を大きくさせないことに繋がります。
後ほど解説しますが、被害金返還のためにも、詐欺師に気付かれないよう証拠を確保した後、そっとフェードアウトして、返金に向けた準備を進めるのが賢明ではないでしょうか。
相手に詐欺に気づいたことを悟られないためにも、今後の対応について、特殊詐欺事案の経験が豊富な弁護士に助言を求めることを推奨します。
「偽逮捕詐欺」で口座振込による詐欺の被害金を返金してもらうためには
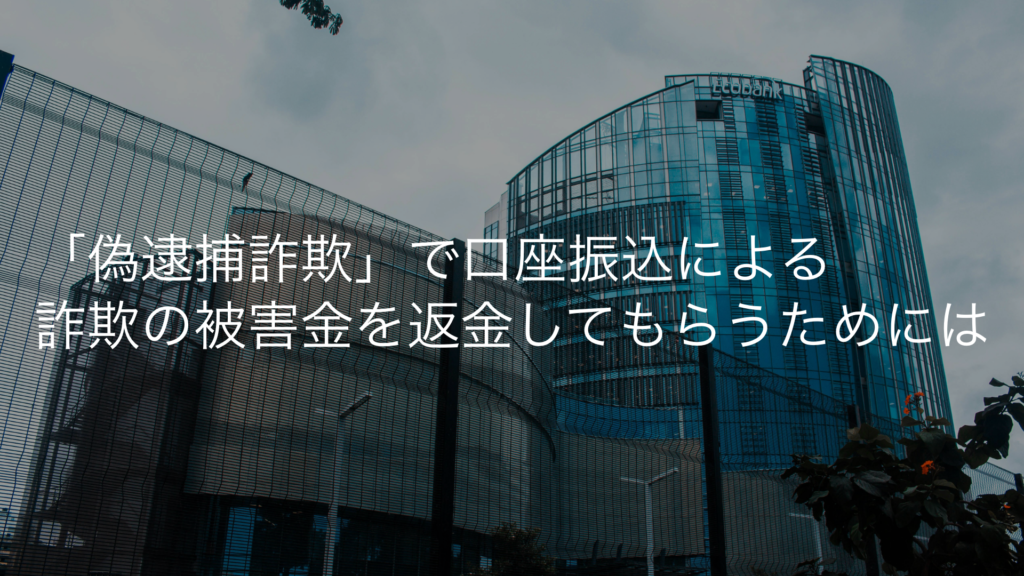
偽逮捕詐欺で口座振込をした場合、被害金返金してもらうためには、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」をもとに、法的手続を行う必要があります。
これらの手続の対象となるのは、偽逮捕詐欺をはじめとした一般的な詐欺や振り込め詐欺(オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺)などの犯罪被害に遭い、被害資金の振込をした場合です。
具体的には、振込先の銀行判断で、犯罪被害によって資金の振り込まれた銀行口座を凍結(口座への出入金の停止)し、一定の条件を満たすと、被害者が被害回復分配金(凍結口座の残金)を受け取ることのできるといったものです。
被害回復金受け取りまでの流れ
被害回復金の受け取りには、2通りの流れがあります。
こちらの節でご紹介するには、被害者から直接該当の金融機関に対し、直接申し出る際の被害回復分配金受け取りまでの一般的な流れについてです。
ご自身で「被害回復分配金支払申請」をする際には、必ず期間内に手続を行うことに加え、必要書類を不足しないように準備する必要がある点にご留意ください。
具体的な内容については、次の表をご覧ください。
| 被害回復分配金受け取りの流れ |
| 1. 犯罪被害によって資金の振り込まれた銀行口座が凍結される。 |
| 2. 預金保険機構のホームページに該当口座の情報や口座名義人の氏名などが公開される。 |
| 3. 公開後、60日以内に「自己の権利行使」を主張する届出がない場合、口座名義人の権利が消滅する。 |
| 4. 被害者からの「被害回復分配金支払申請」の受付が開始される。 |
| 5. 被害者は、90日の被害回復分配金支払申請の期間中に、振込先の金融機関に対して申請をする。 ※申請書は、最寄りの該当金融機関で請求できる。また、預金保険機構や金融庁のホームページからもダウンロード可能。 ※ 申請の際には、次の書類を揃える必要がある:本人確認資料(運転免許証や健康保険証の写しなど)、振込明細の写しまたはその振込が記帳されている通帳の写し、警察への被害届の受理番号、振込の原因となる書類の写し(振込を請求された際の証拠)など |
| 6. 金融機関が支払該当者を精査し、被害回復分配金受け取りとなる。 |
理由としては、詐欺被害者が複数人いる場合、被害回復分配金は被害額に応じ、各被害者に配分されるためです。
また、詐欺師がすでに口座からお金を引き出してしまっており、口座残高が1,000円未満の場合、被害金の返還の対象とならないことにご留意ください。
弁護士からの通報による口座凍結も可能
公的機関(警察等の捜査機関・金融庁・消費者センター・弁護士会)や弁護士、認定司法書士からの通報により口座凍結する方法があります。
特殊詐欺の被害者が公的機関や弁護士などの専門機関に相談し、相談先が該当の金融機関に対し、書面または電話により通報するといった形です。
弁護士からの通報する場合には、振込明細の写しとともに、日本弁護士連合会制定の統一書式により申請を行います。
また、銀行口座に関する情報しかなくても、裁判所や弁護士会の照会(弁護士法 第23条)により、相手方の住所を特定しての直接交渉や、警察との連携による捜査など、様々な手段で被害回復のためサポートが可能です。
従って、公的機関と併せて、弁護士による情報提供は、口座凍結される傾向が高いとされています。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「偽逮捕詐欺」に遭った場合の相談先

こちらの章では、偽逮捕詐欺の被害に遭った場合の相談先についてご紹介します。
万が一、被害に遭われた際には、早急に下記の機関に助けを求めてください。
重ねて、ご自身で詐欺であるか判断がつかない場合、実際に振り込みをする前に、家族や友人をはじめ、信頼できる人物に相談するよう徹底しましょう。
1. 国民生活センター・消費者ホットライン
偽逮捕詐欺をはじめ、事件の当事者になると、動転して、何に困っているのか分からなくなってしまったり、大きな不安や恐怖感に襲われるといったケースも少なくありません。
国が運営する独立行政法人である「国民生活センター」とは、消費者の権利や法律に関する情報提供や相談支援を行っており、専門の相談員が適切な対処方法や法的解決手続についてアドバイスを提供してくれます。
犯人の連絡先が判明している場合には、間に立って連絡を取ってもらえるケースもあるため、専門機関の力を借りることも推奨します。
国民生活センターでは、消費者が安心して生活できるよう、電話での無料相談も可能です。
さまざまなサポートを提供しているため、今後の対応について、アドバイスを仰ぐのも一つの選択肢ではないでしょうか。
【国民生活センター】
- 電話番号:03-3446-1623
- 受付時間:平日10:00~12:00、13:00~16:00
- 公式HP:https://www.kokusen.go.jp/map/
消費者ホットライン
偽逮捕詐欺について、どの機関に相談すれば良いかわからない場合、最寄りの相談先を紹介してもらえる消費者ホットラインに問い合わせましょう。
地方公共団体が設置している、消費生活センターや消費生活相談窓口を紹介してもらえます。
【消費者ホットライン】
- 電話番号:188
- 受付時間:相談窓口により異なる
- 通話料金:無料
- 公式HP:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline
2. 警察
偽逮捕詐欺をはじめとする詐欺行為は詐欺罪に該当し、10年以下の懲役が科せられます。
特に、警察などの公的機関からの現金や預貯金通帳、キャッシュカードを渡すよう求められた場合、話をそのまま信じてしまう方も多いことでしょう。
実際に被害に遭った場合はもちろん、詐欺と思しき事例に遭遇した際には、警察に相談することを躊躇せず、次の情報を伝えましょう。
- 「偽逮捕詐欺」に遭った流れ
- 現在の状況詐欺師の情報(携帯番号やメールアドレスなど)
- 契約書などの書類(守秘義務契約書など)
- 詐欺の取引日時
- 詐欺の被害額
- 振込の明細書
- 銀行口座の取引履歴(店番号・口座番号・氏名など))
相談する際には、「#9110」に問い合わせましょう。
※「110」は、すぐに警察官に駆けつけてもらいたい緊急の事件・事故などを受け付ける通報ダイヤルです。
詐欺の被害を的確に報告することで、相談内容に準じて、今度の対応についてのアドバイスをはじめ、状況に応じて、詐欺師への警告や検挙などの措置を行ってもらえます。
重ねて、実際に警察署へ行かれる際には、日付やURLが紙面に残せるため、証拠資料をプリントアウトして、紙の状態で持参しましょう。
ただし、被害金の返還手続は管轄外のため、弁護士に依頼することを推奨します。
【警察】
- 電話番号:#9110
- 受付時間:平日8:30~17:15(各都道府県警察本部で異なる)
- 「#9110」の紹介ページ《政府候補オンライン》:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.htmll
「偽逮捕詐欺」の被害が拡大する前に弁護士へ相談しましょう
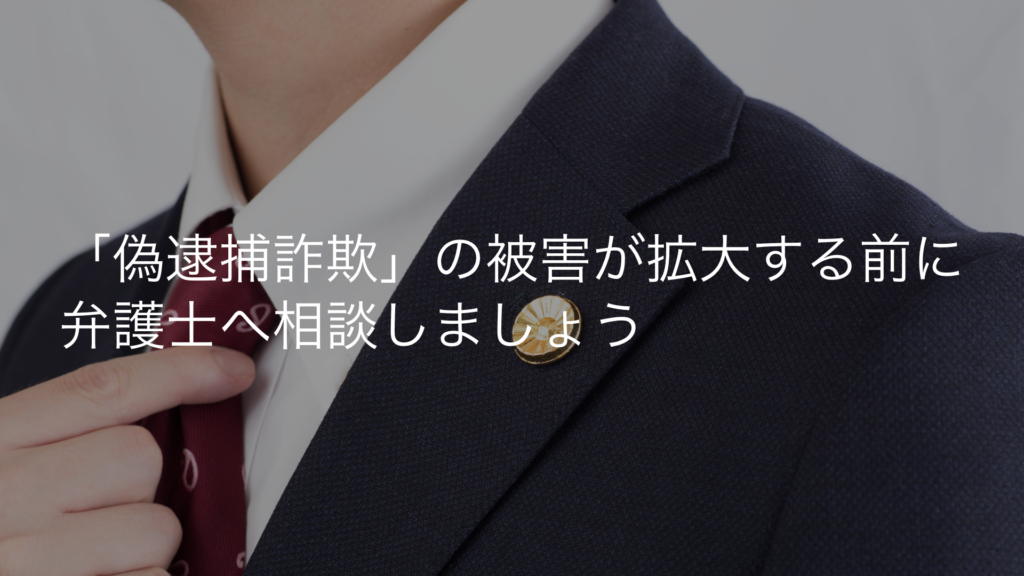
1. 「最適な解決方法」で問題解決へアプローチ
弁護士に相談することで、偽逮捕詐欺の被害に直面した際にも、最も適切な解決策を見つけることができます。
弁護士は法的観点から状況を分析し、客観的かつ冷静な視点で問題を捉え、解決策を提案できるため、感情的になりがちな場面においても、専門家のアドバイスをもとに、冷静に対処することが可能です。
煩雑な手続や返還手続に関する書類作成、金融機関との交渉、さらに被害者本人では相手方や口座名義人が応じない場合も、代理人として介入することで、問題解決をスムーズに進めることができます。
また、弁護士は詐欺事案に関する業務の幅に制限がなく、裁判が必要となった場合でも、迅速かつ効果的な対応が期待できます。
特に、詐欺事案の解決を得意とする法律事務所では、経験豊富で相談実績も多いことから、相談者の頼もしいサポートとなるのではないでしょうか。
2. 被害金の返還請求手続を代理してもらえる
詐欺師および口座名義人から返金を求める場合、つまり詐欺問題解決には、スピード感を持って対処することが最も重要なポイントです。
警察や消費者センターなどの機関は、詐欺事件の捜査や犯人の逮捕、適切な対処方法についてのアドバイスは可能ですが、被害金の返還請求は管轄外です。
一方で、弁護士であれば、被害金の返還請求に関する手続を請け負うことができます。
相談者様と詐欺師本人だけでなく、口座名義人の間での交渉が難航する場合でも、弁護士の交渉力が加わることで、円滑に物事を進められるのも大きなメリットではないでしょうか。
弁護士には、法的関連で対応可能な業務や裁判所・審理の制限がないため、相談者の状況に最も適した手段で、問題解決へ向けアプローチを講じることが可能です。
3. 刑事告訴や民事責任の追及を行う際の手続をサポートしてもらえる
偽逮捕詐欺で刑事告訴する場合、その手続や警察とのやり取りには、法的知識はもちろんのこと、独自のノウハウが必要不可欠です。
弁護士は、法的な手続や訴訟に精通しており、適切な法的戦略を立案し、返金を求めるプロセスを円滑に進めることができます。
弁護士に依頼することで、内容証明の送付や警察への被害届提出、その後の対応まで一任できるなど、スムーズな問題解決や精神的負担を軽減する一助となるのではないでしょうか。
重ねて、振込先の口座に残高がなく、そこから被害金の分配を受けることができない場合に、民事責任追及のため、口座名義人に対し損害賠償請求等を行うことも可能です。
必要書類の準備や作成、相手方との交渉まで請け負ってもらえることから、相談者の時間と手間を削減することにも繋がります。
また、直接出向かなくても、LINEやフリーダイヤルでの電話相談を無料で受けてくれる法律事務所も増加傾向にあります。
法律の専門家である弁護士の知識と経験を頼りに、あなたにとって最適な対応策を見つけましょう。
まとめ

いかがでしたか?
ここまで、「偽逮捕詐欺」について最新の手口を踏まえ解説させていただきました。
繰り返しとなりますが、偽逮捕詐欺とは、スマートフォンの通話アプリを利用し、携帯電話や預貯金口座の不正利用を名目に、警察官を騙り逮捕を示唆し、金銭を騙し取る詐欺のことです。
被害者を騙すため、社会的信用度の高い公的機関の職員を騙り、被害者を心理的に操作し、詐欺を働く悪質な手口のため、注意が必要です。
被害を未然に防ぐためにも、偽逮捕詐欺の流れをおさらいしましょう。
- スマートフォンの通話アプリに公的機関の職員から電話がかかってくる
- 公的機関の職員から警察に電話を転送され、被害届の提出を求められる
- 在宅での調書
- 別の容疑がかけられる
- 捜査を進めることを名目にした「LINE」でのやり取り
- LINEで重要データが送付される
- 厳しい追及
- 資産リストの提出を要求される
- 資産リストの提出を拒否すると「逮捕する」と脅される
繰り返しとなりますが、こちらの手口は、総務省や警察官をはじめとする公的機関の職員を名乗り、「逮捕」を示唆することで、揺さぶりをかける手法を用いて、口座情報等を騙し取るものです。
詐欺であるか判断が難しい傾向が高いため、自分1人で問題解決しようとせず、必ず家族や友人などの第三者に助言を求めるよう心掛けましょう。
万が一、詐欺の被害に巻き込まれた場合には、身近な人に打ち明けづらい場合をはじめ、被害を拡大させないためにも、警察等の公的機関や法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
※こちらの記事は、2024年6月17日時点の情報です。
お問い合わせ先
【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
- 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
- TEL:0120-239-235(詐欺問題専用番号)
- ホームページ:https://sagihigai-henkinsoudan.jp/illust02/02/g/lad/